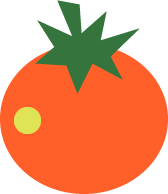ベッド作り
こんばんは、とらパパです。
今北海道で一番の話題と言えばビッグボツ。いやビッグボス。連日のパフォーマンス、言動の注目度の高さはローカルニュースを見ていても感じられます。
昨年、ビッグボスが監督就任会見で「優勝なんか目指しません」という驚きの発言があり、えっ?と思った方は多いと思います。最近も「開幕3連戦は遊びます」という発言で賛否がありました。
私は「おお、なかなか衝撃的だな」と思ったのですが、一方で確かにビッグボスのいう通りかもしれないとも思いました。
私は野球好きであるものの、野球の試合結果次第で明日の暮らしや人生が変わるわけではないので、野球=娯楽=遊びという構図であることは間違いないのだなと。
今後も驚きのコメントが数多く出てくると思いますが、しばらく経ってからビッグボスの言う通りだった!という日が来るかも、いや来ないかもしれません。
「ファンは宝物」なら、派手なパフォーマンスやセレモニーよりも「勝利」が何よりのファンサービスだと古い野球ファンは思うのですが、もしかするとビッグボスの目線はさらに先を行っていて私はまだ追いついていないだけなのかもしれません・・・。
今年のファイターズがどうなるかはまだ未知数ですが、話題作りで楽しませてくれそうですね。
さて、ここ最近は4月に定植を行うハウスの準備(ベッド作り)を進めています。
写真を撮り忘れたのですが、先々週プラソイラーという機具を使ってハウス内の土を砕く(割る)作業を行いました。これによって、圃場(ほじょう)の排水性や透水性、通気性を向上させる効果があるとのことです。
この土を砕く器具ですが、種類がたくさんあります。私が今回使ったプラソイラーを始め、サブソイラー、パラソイラー、ハーフソイラー、バイブロソイラーなどなどです。自分の圃場の特性に合わせたり、目指す土づくりの方向性によって選ぶようなのですが、正直どれが良いのか現時点では答えが出せません。
その後ハウスに丸1日水を打って土に水を含ませ、数日乾かした後にトラクターで耕起します。耕起した後は畝立ての準備です。
畝を立てるためにはあらかじめ畝幅と通路幅を計算しておく必要があります。畝を立てた後に、こんな通路幅じゃ収穫や作業ができない・・・とならないためです。
そのためハウス内の幅や畝立て機で成形される畝の幅を測ります。先輩農家は毎年の作業なので、自分専用の治具を使ったり、畝ごとに水糸を張ったりと自分のやりやすいやり方がだいたい決まってます。
私は昨年いくつかの先輩農家に聞いたり、見学したりしてやってみたいと思った方法で準備をしていざ畝立てです。

昨年6月頃、親方Wさんのところでやらせてもらって以来の操作となり、どうなることかと思っていましたが、意外にあっさり畝を作ることができ一安心です。まっすぐではなかったり、高さが違ったりする場所がありますが、これが現在の実力なので仕方ないですね。。


(人によって順序が違うことがあります)
今回の私のやり方ではマルチを敷く作業は基本的に2人で両側を引っ張りながら行います。その方が効率が良いからです。ところが、途中とらママが抜けなくてはならなくなり残り半分は私1人で行いました。
1人でもできないわけではないのですが、作業スピードがガクンと落ちだいぶ時間がかかってしまいました。

この後通路にはみ出しているマルチに土をかけます。
とここまで順序を書いてきましたが、この一連の作業も各農家でやり方が違っておりこれが正解というものはありません。自分が研修する親方のやり方に習うという形が多いようです。
マルチを張る作業を1人でやって身に染みたのですが、できるだけ1人で効率的にできる作業を増やすことが重要だと改めて思いました。
夫婦で新規就農する場合に2人いないとできない、効率が悪いという作業があるとどちらかに何らかのアクシデントがあった場合に片方に大きな負荷がかかってきます。
私たちで言うと息子がまだ小さいので土日祝日の作業、熱を出してどちらかが家にいなければならなくなった時(平均すると月に1回くらいあります)、保育園の長期休みなどがそれにあたります。
これをうまくかいくぐるスケジュールを組むのと、もし何かあっても最低限のダメージで済むにはどうすれば良いか。スケジュールに余裕を持たせるのが一番ですが、それ以外に例えば畝立準備方法の簡略化だったり、畝立機で3つのことを同時にやる…など先輩農家を訪問するといろいろなヒントが見えてきます。
その中で自分に向いていると思う方法を試す・・・というのが今シーズンの私の研修内容になります。また、これがベストと思ってもより良い方法、効率的な方法をやっている方が必ずいるので、絶えず情報収集は継続していきたいと思います。
ベッド作りはまだ続いているのでまた書きたいと思います。